| 2008年度へ |
![]() エッセイ
エッセイ
■おもてなし
2007年12月12日(水)
 |
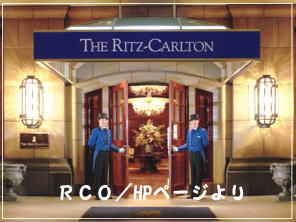 |
| 先般、二カ所で「おもてなし」を受けた。一つは京都・祇園の「一力亭」、もう一つはその時の宿泊先になった「リッツカールトン大阪」だ。「一力亭」は、今更言うまでもないが、有名な一見さんお断りの老舗茶屋であり、かたや「リッツカールトン大阪」は、地元阪神電鉄がその経営の主体を握っているものの、ホテルランキングでは一位に輝く、こちらも人気ホテルだ。特に「一力亭」は、現在は京都の旅館やホテルなどの紹介でも予約が可能なのだそうだが、それでもふらりと行って入れるお茶屋ではない。今回は勤務先の社長のご好意で同席させていただいたが、この店の常連客の名前を聞くと、やはり日本一と言われるこの店の格式の高さが伺われる。 「一力亭」と「リッツカールトン大阪」、この両者に共通しているのは、来客に対しての「サービス精神」と「おもてなしの心」、いわば、如何に客をもてなし、客に喜んでもらえるか、その一言に尽きる。これらを一般に「ホスピタリティー」と呼び、各業種に当てはめ置き換えをするセミナーや研修が各地で大はやりだが、そのモデルに取り上げられるのが「リッツカールトン大阪」である。しかし、このホテルを幾度も利用しているリピーター客が、こんなサービスを受けた、従業員がこうしてくれた、素晴らしかったという言葉をそのまま期待して訪れ、自分にはそんなサービスはしてくれなかったという不満もあるのも事実。だから、この「ホスピタリティー」で有名になってしまったホテルのスタッフたちの心遣いの有り様は日々さぞかし大変だろうと思う。 さて「一力亭」で、どうして一見さんがお断りなのかというと、これはこの種のお店の支払いがその場の現金払いではなく、後に一括して請求が来て支払うシステムになっている為に信用が重んじられるからである。先のホテルのサービスに対しての不満も、恐らくその人が常連客になれば解決することだろう。サービスを提供する側からすれば、いつも利用してくれる客と、初めての客、勿論、そのホスピタリティーに差別はないけれど、そこは人情、人間の意識下でおのずと区別が付いてしまうというのは責められることではないだろう。(和) |
■連載小説
2007年11月22日(木)
 |
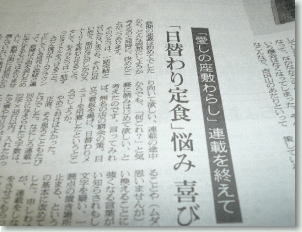 |
| 新聞はA社を取っている。物心付いた時からこの新聞は家にあり、漢字は難しくても四コマ漫画などを読んでいたから、購読年数はもう半世紀にも及ぶだろうか。時々、他社の新聞を読むことがあるがどうも読み慣れず、居心地の悪い椅子に座っている様な気分で、どうしても個人の好みとしてA社になってしまう。 新聞を読む楽しみは人それぞれだが、私の楽しみの一つは小説だ。まずはコラムに目を通し、興味のある社説を熟読して最後に小説を読む。毎朝わずか千字ばかりのスト−リ−に心を弾ませたり、作者の都合で休みになれば、まるで一食抜いた空腹感を味わうような気持ちにもなりながらも、毎日セコセコと小さな世界を楽しんでいる。 この新聞の連載小説からは、古くは「氷点」や「柝の音」等の名作を初め、世に送り出した小説は枚挙にいとまがないが、今は「愛しの座敷わらし」と「宿神」が掲載されている。特に「愛しの座敷わらし」は文体が平易で大変読みやすく、毎日どこか心に響くフレーズがあって、そのテーマも「家族の再生」かなど得心しながら読んできた。そして迎えた最終回にはなんとしゃれたオチが付いていたことか。「成る程、そう来たか」とニンマリしながらもこの小説が終わった寂しさはぬぐえない。後日談で、作家の荻原浩氏のこの連載への苦労話が書かれていたが最も努力を要したのは字数制限だったという。プロの書き手でもそんなご苦労があるのかと興味深く読ませていただいたが、連載物を最後まで読み通すには、作者の力量もさることながら佳境に入るまでの読み手のある種の辛抱も必要になってくる。この辛抱いかんで最終回の感動を味わえるかどうか作者と同様読者にもそれなりに努力がいるものだ。(和) |
■「神戸ルミナリエ」
2007年10月31日(水)
 |
 |
| 1995年12月から始まった神戸ルミナリエが今年13回目を迎える。13年前のあの日、ニュースで地震を知った私は母に電話がつながらず、最悪のことを頭に描きながら神戸へ車を走らせた。住んでいるマンションも母も無事だと確認できた時は、天を仰ぎ神に感謝をしたが、6000人以上もの人が亡くなり、壊滅的な打撃を受けた神戸の街の様子がテレビで報じられた時は涙が流れて止まらなかった。そして、その年の12月、「阪神淡路大震災」と命名され、この地震で亡くなった人への鎮魂と街の復興を願って開催されたのが「神戸ルミナリエ」の始まりだ。当初は東京で予定されていたクリスマスのイベントだったらしいが、急遽神戸に変更になったのは当のプロデューサー今岡寛和氏の出身地が神戸であったことを思えば、その開催に関係者の深い思いやりを感じることができる。 私は第一回目から10年間ルミナリエを見続けてきたが、初年度、初めて光が点灯された時の感動は今でも忘れられない。きらびやかな光の回廊に6000人の魂の輝きを見つめ、人々は心底鎮魂を捧げた。手を取り合い身を寄せ合って涙を流すお年寄りもいた。当時神戸の復興には10年かかると言われ、それならば私もこれから10年間このルミナリエに通い、せめて亡くなった人たちへの鎮魂と神戸の再生を祈ろう、そんな熱い思いを抱かせる程、この光の下には故郷を思う人々の強い一体感が溢れていた。 あれから13年、ルミナリエは年々観光化し、通り道一帯は大混雑で、会場に着くまでには点灯時間が終わってしまう、ということも起こっている。又、「ルミナリエ」に対する人々の思いも様々に変遷し、皮肉にもこれが街の復興の証しなのかとも思う。突き当たりの東遊園地に備えられた募金箱に毎年千円札を1枚入れて帰った私の10年間はこうして終わったが、復興した故郷の街に帰ることのない人々への鎮魂は永遠に忘れることはない。(和) |
■イタリア語雑感
2007年9月20日(木)
 |
 |
| イタリア語を学んでいる。一週間に一度、たった50分の講義ながら仕事を終えて教室に向かうのには結構気力がいる。休むことも多く、その分自習をするかというとそれも思うに任せない。だから、修学3年目を迎えても語学力は遅々として進まず何度も挫折しかかる。それでも、なんとか続いているのは、教室の雰囲気と明るく陽気なイタリア人の先生の指導のお陰だろうか。 この教室は市内の狭いビルの一室で、独語、仏語などのヨーロッパ言語と英語を教えているが、先生達が全てその言語の出身者であるのと、小さい学校ながら経営者の理念がしっかりしているのであろう、生徒も教室の規模に見合わず多くいる。そんな教室で一緒に勉強しているひろこさんは、20代の若い女性だけれど一人前のパテシエだ。お菓子作りの修業の為に来月イタリアに留学をするので、学ぶ姿勢も真摯でいつも感心させられる。 翻って私はというと、この言語を学ぶ目的が実に曖昧だ。何年か前に訪れたフィレンツェで、もっとゆっくり美術館巡りをしたい、広大な歴史の広がる街々を一人訪ね歩きたい、その為に少しでも現地の言葉を話せたら…などという低レベルなものだから、当然学ぶ態度もそれなりになる。人は目的が明快であればあるほど集中力が増すものだけれど、10月にある検定試験を目標にしてしまった私はひたすら文法を覚えることに神経を取られ、かつて経験した受験勉強再現の日々をここしばらく送るはめになっている。件のひろこさんは、半年の留学後、どんなにか語学力が増しているかと思うと羨ましい気持ちになるが、今は私なりの目標を定めた以上、まずは達成するしかないだろうと今夜も眠い目をこすりながら机に向かっている。(和) |
■盆灯籠
2007年8月14日(火)
 |
 |
日中気温が35度を超える猛暑の中、お墓参りに行ってきた。自宅から中国自動車道を走ること約2時間、三次(みよし)と呼ばれるこの辺りは、高級ぶどうのピオーネの産地であり、近くにワイナリーもあって観光客もそれなりにあるが、それでも、道路が整備された以外はこの30年、大して変わりのないのんびりとした田舎だ。そんな三次盆地の小高い山の一角に墓所があるのだが、土地の人たちが墓所の周辺をいつも綺麗に清掃し、お盆に入ると竹の骨組みに、赤や青のカラフルな色紙を付けた広島独特の盆灯籠をそれぞれのお墓に立てて先祖の霊を迎えている。この盆灯籠は、江戸の頃、旧市内の浄土真宗安芸門徒の人達が始めた習俗が今に伝承されたものらしいが、広島の夏の風物詩にもなっていて、どこのお墓にもまるで七夕かとみまごうばかりヒラヒラと色紙が垂れている。 結婚して初めての墓参りをするのに、この盆灯籠を買って来るように叔母から頼まれた私は、鮮やかな色の付いた灯籠の中に、真っ白で清楚な感じのする灯籠を見つけて、何の迷いもなく、その白い灯籠を数本買って行った。私の故郷の神戸には盆灯籠を立てる風習など勿論なく、こんな派手で始末に困る灯籠(風が吹くと簡単に倒れる、雨が降ると色紙はすぐに取れて色落ちし服にでも付いたら取れない)を立てるということに、私自身どこか敬遠したい気持ちがあったのだろう。果たして、まっ白の灯籠を抱えて意気揚々と墓所に着いた私は、叔母達から大いにひんしゅくを買うはめになった。 実はこの色の付いた灯籠は先祖や過去に亡くなった人の為に立てるもので、白い灯籠は新盆を迎える人の魂を慰めるためのものであったのだ。知らないこととは言え、お墓の周りに数本も白い灯籠が立てば、今年一体誰がそんなに亡くなったのかと不審にも心配にもされ、なんと人騒がせなことになっただろう。最近は、環境や防火に配慮して、灯籠を立てないようになってきたが、この時期、墓参に来るたびに、遠い昔の私の所業を思い出しては苦笑している。(和) |
■エジプトの記
2007年7月24日(火)
 |
 |
| 先般の旅行先、エジプトには「バクシーシ」という慣習がある。これは「富める者は貧しい者に施しを与えよ」というイスラムの教えで、エジプトのみならず中近東諸国の共通用語でもあるらしい。成る程、空港や街角で観光客相手に金品をねだる人達はそこかしこに居た。私達も旅行中、何度もこのバクシーシの要求を受けたが、ツアーの添乗員や現地ガイドの適切な対応のお陰で、他に聞くように困ることにはならなかったので、大した感慨を持つこともなく旅行は終わろうとしていた。それが日本へ帰る間際になって深く考えさせられることになる。 出国直前、カイロ空港でトイレに入った私は、入口でトイレットペーパーを手渡してくれ、ドアを開けてくれた女性に慣習通り、チップとしてお金を渡そうとしたのだがLE(エジプトポンド)は使い切っていたためにまさしくお金がない。そこでポケットにつっこんでいた1USドルを渡したのだが、その様子を見ていた現地の他の女性が自分にもくれという。彼女からは何のサービスも受けていないのではっきりと断ればよかったのに、このトイレを掃除してくれているのだとつい1ドルを渡してしまった。すると又黒衣を纏った違う女性が入って来て「バクシーシ、バクシーシ」と身振り手振りで私に訴えるのだった。私は、もう日本に帰るのだし、1ドルはたかだか120円(この場合チップは10円程度でよいのに)…、という実に安易な気持ちで再び1ドル札を差し出したのだが、なんともいえない後味の悪さが残ってしまった。 実は、旅行に出る前に読んだイスラムに関する本の中で、過激派と目される一部の人たちがテロを起こす原因の一つは、神聖なるイスラムの教えを外国人が踏みにじる為だと書いてあったことを思い出したのだ。本来バクシーシというのは、もしかすると私たちが思っているよりもっと崇高な互恵精神なのではないか、他国の者がこうして真成る考えも持たずに為す行為が、この国の人たちの宗教心にどんな影響を及ぼすか、と思い至った時には恥じ入るほかはなかった。「郷にいらば郷に従え」という日本の諺があるが、日本でも「郷」に入る時には、その「郷」の十分な理解を得てから入らねばとんだ間違いをすることにも成りかねない。帰国後20日余り、旅の疲れはすっかり癒えたが、帰国直前のこの出来事が澱のように今も私の心によどんでいる。(和) |
■その人のこと
2007年6月20日(水)
 |
 |
通勤はいつもJRを利用している。私が乗車するこの駅は、すぐそばに商工センターやデパート、大型電気店などを擁し、学校や介護施設などもあって、広島の西の外れにありながらも結構便利なエリアになっている。しかしその割には小さなこの駅で、私は大抵朝8時30分頃の電車に乗るのだけれど、やはりこの時間帯が一番乗降客が多いだろうか。 今の会社に勤務して18年、毎日同じ電車で通勤していると、この駅で言葉は交わさずとも顔見知りも出来て、しばらく会わなければあの人はどうしたのだろうかとふっと考えたりもする。もう何年ほど前になるだろう。小柄なその人は、真っ白なスーツを着て、高いヒールを履きヴィトンのバッグを下げて私と同じ車両に乗って来た。一緒にドアのそばに立つと、漂ってくる香水の香りからも品の良さが伺えた。そんな彼女がスーツよりもワンピースを着ていることが多くなり、やがてそれが妊娠しているためだと分かったのは、もう臨月も近かったのではなかろうか。彼女の細見の体型と私の鈍感さとで気付かなかったのだが、恐らく産休間際になっていたのだろう。それ以来駅で会うことはなくなった。 ところが最近、久しぶりにその人を見かけるようになった。体型は少しふっくらし、スーツ姿ではないけれど、背筋をピンと伸ばした姿勢の良さはすぐに彼女だと気が付いた。足元はローヒールになっていて、バッグも大振りなトートを下げている。きっと産休期間が終わり職場復帰したに違いない。あの日と同じドアのそばに一緒に並んだけれど香水の匂いはしなかった。彼女の朝の慌ただしさ、忙しさはいかほどだろう、退社後も買い物をし大きな荷物を提げて大急ぎで帰宅しているだろう、託児所に子供を迎えに行くのかも知れない、などとつい想像をたくましくしてしまったが、これではまるで私はストーカーではないかと苦笑が洩れる。毎日頑張っているだろう彼女の姿にエールを送りたいと思ったけれど、その人は、そんなことはいらぬ大きなお世話だと言わんばかりの姿勢の良さで今朝も私の横に立っていた。(和) |
■松本清張
2007年6月7日(木)
 |
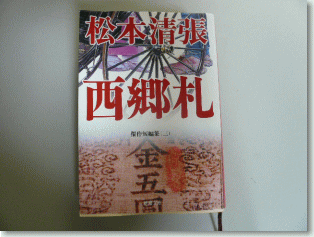 |
何げに立ち寄った古本(最近はリサイクル本というらしい)屋さんで、松本清張の「西郷札」が目に付いた。清張の処女作だ。学生時代に「点と線」や「ゼロの焦点」、「眼の壁」、「霧の旗」など、夜を徹して読みふけった頃が甦る。どの小説も時代背景を考えれば、現代の若者には理解しがたい面も出てこようが、それでも読むことをお勧めしたい名作だ。中でも私は「ゼロの焦点」に心を揺さぶられた。荒涼とした断崖絶壁が今でも目に浮かぶ。この物語の舞台となる能登の海が見たくて初めて一人旅をしたのも懐かしい。 松本清張は、社会派の推理小説家として’50年代半ばから次々と作品を発表しているが、大変陳腐な表現ながら、どの作品も運命に翻弄される低下層の人々に自身の生い立ちを重ね共感を寄せているものが多く、私はそれが清張なりの深い人間愛なのかとも思う。文章そのものも読者に無駄な空間を与えず読破させてしまう筆力は単なる推理小説の域を超える。 ところがある時点から清張の作品に私は違和感を抱くようになった。60年代に執筆された「彩り河」に至っては、読み始めて数行でこれまでの清張の作品にはない稚拙な行間に苛立ちを覚えた。最後まで読み通したものの、この小説は清張らしい重厚感もなく、期待を裏切られた作品だった。これ以降、私はまるで憑きものが落ちたように清張の小説は読まなくなったが、実はこの60年代には、清張自身、書痙(しょけい:手が震える病気)を煩っていて、執筆は口述筆記がなされていたこと、又、平林たい子が、清張の多作ぶりに「複数の助手作家を使った工房形式で作品を作っているのではないか」と言う見解を持ったことなどを後に知り、私なりにやっとあの時の違和感に終止符が打てたのだった。今年は清張没後15年、気に入りの作家に対して一ファンがとやかくかまびすしいのは世の常なので、こうした感慨にふけるのも笑って聞き流して頂ければと思う。(和) |
■バンビーノ
2007年5月30日(水)
 |
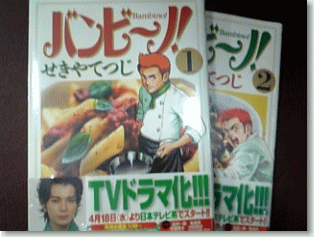 |
テレビドラマ「バンビーノ」(水曜ドラマ)を楽しみに見ている。福岡から上京した大学生が、イタリア料理人を目指して修業する物語だが、青年の成長を通して、人間の学びに必要なものは何かを教えられる。主人公伴省吾は、福岡のイタリアレストランでアルバイトをする大学生、地元の常連客からは、料理が上手い、センスがいいと評判だ。そんな伴に持ち上がった東京の有名店でのヘルプの話。伴は勇んで上京するが、そこで見たものは、伴のそれまで培ってきた料理の技術やプライドを粉々にしてしまう。 このドラマの原作は漫画だが、ドラマの中でもスピーディな話の展開は見ていて飽きない。原作では登場人物にもそれぞれにエピソードがあるのだが、テレビでは主人公にのみ焦点が当てられ、それ故にこうした登場人物の多い物語が散漫になりがちなところを引き締めている。そして、何より見ていて気持ちがいいのが、伴青年の「素直さ」だ。怒ったり落ち込んだり投げ出しかけたりするが、失意の内にも何が悪かったのかを自省する。人は、誰でもプライドや意地を持って生きているが、それが認められなかった時にいかに素直な気持ちで周囲の助言や意見を受け容れられるか。あの経営の神様と言われる松下幸之助が「素直さ」について、『失敗の原因を素直に認識し、「これは非常にいい体験だった。尊い教訓になった」というところまで心を開く人は、後日進歩し成長する人だと思います』と述べているが、伴青年の素直さはまさにこれに当たる。 題名のバンビーノとは、伴青年の未熟さをイタリア語の幼児(バンビーノは5歳くらいまでの男の子の意)の意味で付けられたものだが、自分はまだまだバンビーノ(男の子)、バンビーナ(女の子)だと心得て、いくつになっても「素直な心」を持つところから成長と進歩があるのだと、毎週伴青年から教わっている。(和) |
■あんちゃんに寄せて
2007年5月23日(水)
 |
 |
新潟のフラットコーテッドレトリーバー、あんちゃんが白血病で急逝した。享年2歳10カ月。発症したのがいつなのか定かでないが、異変に気付いて診察を受けてからわずか10日足らずで逝ってしまった。余りにも若過ぎる年齢、余りにも劇症に進んだ病に、担当の医師とて、為すすべもなくただただ見守るしかなかったようだ。一般に白血病は、血液細胞の腫瘍であり、全身に腫瘍細胞が存在することから治療は大変難しいと聞く。人間であれば、骨髄移植や制ガン剤の投与など最新の医療技術で完治も望めるが、獣医学では治癒した例は過去一例もないそうだ。 あんちゃんは、アルファも何度か一緒に遊ばせてもらったが、天真爛漫で明るく、まるでひまわりのような元気な女の子だった。飛び跳ねるのもボールを追いかけ走るのも、その姿は病などとはおよそ無縁で、今でもきらきら輝く生命の固まりのような印象がある。そんな彼女を突然襲ったこの病。発症のメカニズムはどうか。真摯に研究を貫いても治療の方法は見つからないのか。 この病だけではない、全ての犬の難病を珍しい症例だったと個々の病院でカルテを閉じるのではなく、治療と研究に向けての積極的なデータベース作りに飼い主の声もボトムアップして貰えないか、そしてそのデータベースを全国の獣医師がネットワークを組んで共有する中で、例えわずかでも治療の方向性を見い出す役割の一端を私達飼い主も担えればと思う。病の発症から臨終に到るまで愛犬の様子をつぶさに見ているのは飼い主だ。私たちは悲しみを堪えながらでも、その為の情報提供なら惜しむことはないだろう。(和) (あんちゃんのご冥福を心よりお祈り致します) |
■娘の結婚
2007年5月12日(土)
|
| その日は、主人にとっては青天の霹靂だったろう。「付き合っている人がいるから、父さん、会って欲しい」と言う娘の言葉に気軽に応じたけれど、果たして、彼は娘に連れられ、身長182センチの身体を気の毒なくらい小さくしてやってきた。真新しい紺の背広姿で、娘さんと結婚させて欲しい、という話から次々出てくるのは、住むマンションまで決まった二人のシナリオだった。娘のたっての要望で、入籍はするが式は挙げないともいう。全て二人の仕事の都合に合わせてスタートする新しい人生になんの異論もないけれど、やはり心を落ち着かせるのに私たち夫婦は数日を要した。 思えば娘を育てるのに、私達は一度たりとも勉強をしろとは言わなかった。ぬいだ履き物を揃えること、お箸はちゃんと使うこと、挨拶をすること、そして綺麗な文字を書くことの4つと、あとはひたすら心身共に強く強く育ててきたが、しかし、ここへ来ていささか強く育ちすぎたか。諸々の思いが横切るけれど、自分の人生だ、潔く生きるがいい。私は、花嫁道具の一式を娘と一緒に買いそろえる楽しみを味わせて貰ったが、ウェディングドレスに身を包んだ我が子の手を引いて、バージンロードを歩くという主人の夢は見事に打ち砕き、娘は元気よく家を出ていった。(和) |