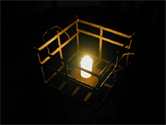Poem & Essay
灯り 空間の風景より
気が向くと、ときどき小一時間ほどの散歩に出かける。道順はここ五、六年ほとんど変わっていない。
その途中、中野の新井薬師寺の山門周辺に新井商店街がある。その一角にいつの頃からか、骨董の店ができた。置き看板に「思無邪(しむや)」と書かれている。どこの町にも、一軒くらいは、いわゆる古道具屋というものがあって、店先から棚天井までガラクタのような日用雑貨の類が雑然と積み上げられている光景を見かけるものだが、この店は違った。品数は慎ましく数えるほどだ。私は特に骨董趣味があるわけではない。しかし、ちょっと入ってみようかと気を引かれる雰囲気があった。ただ、こういう店はだいたい高価なものしか置いていないものだ。見るだけというのも気後れがして、いつも何となく敷居を跨ぐ一歩が踏み出せず、通りすがり外からちらと覗くだけであった。
ところがあるとき、音楽の仲間がこの店に琵琶があると教えてくれた。「琵琶がある」と聞くとまるでパブロフの犬のような状態になる。本能が目覚めて、躊躇という停滞はどこかに消えた。残念ながら、楽器は私の期待していたものではなかったが、店の主人と琵琶について少しく会話を交わし、面識を得ることになった。
それから数ヶ月後、いつものようにその店の前を通りかかると、入口横の半間ほどの見世棚に和紙の張られた灯りが在って、中に小さな白熱灯がともっている。
鉄行灯(てつあんどん)であった。
かねて灯りには少し興味があった。ガラス越しによく観察してみると、鉄は古錆びて表面に無数の凹凸ができている。なかなか良さそうな鉄だ。かたちは、一尺四方くらい、高さ半尺ほどの箱形で、四つの側面は、三分ほどの丸棒と四分ほどの幅に薄く細長く延べた鉄を田の字に組んでいる。鑞付けのようだ。持ち運びに供したのであろう、二つの側面には大きな取っ手が付いている。天はない。底面の四隅からは、がに股の足が踏ん張っていてユーモラスだ。興味いのはその先端の曲がり具合が一本々々異なっていて、段々巻き上がっていることであった。一番巻き上がっている足は、錆びて朽ちてしまったのか、それとも初めからそうなのか、途中が折れそうなくらい細くて華奢だ。鉄幅が広いわりに無骨さをあまり感じさせないのは、多分この四本の足の遊び心のせいだろう。足の高さが違うのか、箱は少し傾いている。これがかえって、わざと捻りを加えた陶器のような興趣を添えている。
私は心を動かされた。
しかし、これは屹度、値が張るに違いないと思い、またその時は、値が張ってでも買い求めるだけの心づもりもなかった。今度通りがかった時にはもうあるまいと思いながら、未練を残して立ち去った。
日を置いて次に通りかかったとき、その行灯はまだ売れずに在った。つぎの時も在った。暫くそれは売れ残っていた。
私は、店の前を通るたびに、この灯りに未練の一瞥を重ねた。
この鉄行灯は今、私の手元にある。店の主人によれば江戸後期から明治初期頃のものらしい。
電球とソケットは当然外した。張ってあった和紙はもちろん当時のものではない。水をしめらせながら慎重に剥がし、鉄の骨組みだけにした。その方が趣が一等よい。和紙が張ってあった時は、上から眺めると、本来見られるはずもない裏側がさらけ出されるようで姿が美しくない。それに、いかにも和風という感じが好きではなかった。剥がしてみると、思った通り、鉄のしっかりした骨格の、水平と垂直の力感がどの角度から見ても明確になって鉄の生命が蘇生ったように見える。二つの大きな取っ手も、全体の構造の一部として融(やわら)いでその大きさが目立たなくなった。まるで小さな羽でも生えたかのように微笑ましい。
その夜、部屋の灯りを消して、この鉄行灯の中央に、とりあえず短くて太い洋蝋燭を立て火を点した。
鉄の表情は一変した。
蝋燭の赤くやわらかい炎は鉄膚の内部まで炙り出すのだろうか。炎に鍛錬された鉄は、炎に馴染むのか。箱の内側に揺れる炎に鉄の生命が気色(けしき)立った。鉄の箱は部屋の一角に確固とした空間を造形していた。蝋燭の炎が顕かにしたのである。
空間は光と影によって生まれるのだ。なるほど陰翳とは存在の証ということか。これが蛍光灯の光ならこうはいかないだろう。
そのうち私は、自分がいま視ているものが、行灯ではなく鉄そのもの、そして、その鉄が造形している空間であることに気が付いた。私が店先で見たこの行灯は、まだ行灯であった。私は行灯として買ったつもりであった。それは生活の中で灯りとして機能する道具である。しかし、今私が視ているものは、鉄そのものであり、それが切り取った空間である。蝋燭の炎が私の意識を導いたのだ。意識がものを在らしめる。見えてくるものは、見者の意識の鏡である。蝋燭を点けるまで知らなかった世界が此処にあった。鉄は美しいと思った。その空間に意志の強さを感じた。炎は箱の中心から鉄を照射(て)らし、部屋の壁天井に鉄の骨格の影を映じた。影はときより大きく揺れ動いた。部屋全体がまるでひとつの灯りのようだ。心が落ち着く。特に何を考えるでもないが、哲学者にでもなったような気分だ。灯りとは他でもない、自分の心を燭(てら)すものなのかもしれない。
どれくらい時間が経ったか、蝋燭を消し、部屋の蛍光灯をつけた。鉄は深い表情を失い、それとともに、いまここに在ったはずの空間は一瞬にして消えてしまった。
部屋全体も何とも薄っぺらく貧弱に感じられる。一様に明るく照らされると、物は質感を失い何かしら虚ろだ。空間や存在の意識も希薄になる。考える力までも萎えてくるように思える。しらけた感じだ。現代は闇を失った。その代償は想像以上に大きいに違いない。様々な騒音で静寂を失い、音への微(こま)やかな感性を曇らせてしまったように、溢れる照明の洪水で闇を失い、陰翳を失い、ものの存在の実感が希薄になってしまっているのではないか。科学のもたらした蛍光灯の光は、その恩恵の陰で、日本人の奥ゆかしさを愛でる心を失わせたのかもしれない。
消えた蝋燭の匂いが漂っている。私は静に眼を閉じた。
この鉄行灯が、かつて燭らし出していたであろう、古へ人の深い生活空間に郷愁を覚えた。
(2000.12.10/中村鶴城)