Poem & Essay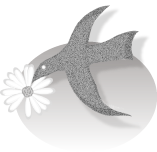
ふたつの祈り
悲劇を語りつがなかった人
1970年代、カンボジアのポルポト政権下での国民大虐殺は、その犠牲者を100万人とも200万人ともいう。さながら地獄絵図のようであったという大粛正。それを逃れてアメリカに渡ったある家族の証言が心に残る。
その家族の親は、アメリカに亡命してのち、その悲惨な体験を心の奥深く封印し、堅く口を閉ざした。孫たちの世代のためである。もし、その悲劇を語りつげば、子供たちの心は恨みや怒りでいっぱいになり、きっと苦しむことになる。何も知らない方が幸せに違いない。そう考えたのである。悲しみは森を包む黒い霧。怒りは燃ゆる砂漠の灼熱。恨みは大地を吹きすさぶ木枯らし。たしかに、かかる情念の中に人の幸せはない。
だが悲劇の体験は、語るも地獄、語らぬも地獄。無念のうちに死に去った者たちの、声なき声が心の闇に谺する。その声が生き残った者をして語らしめる。けだし、その叫びに耳ふさぎ黙したとて、埋火(うづみび)が火照るよう、心の襞をじりじりと焼いて己を責めつづけるだろう。沈黙を選んだ者は、その苦渋を人知れず背負わねばならない。親が選んだのはその沈黙であった。
何も知らず、子供は幸せに育った。しかし図らずも、その事実を知るときが訪れる。親たちが危惧していた通り、子供は深い苦悩にさいなまれる。魂は故国の暗い歴史をさまよった。
* * * * * * * * * *
子々孫々の幸せを願うゆえに、語りつがぬことを決断したあの親の姿が、愛おしく思えてならない。それはひとつの尊い祈りの姿であった。涙がこぼれた。
神に絶え入る大地のごとく
口を閉ざし記憶のふかい眠りにつく
季節はかならず巡る
いつの日か春がおとずれ
凍てついた氷も冬を忘れて地(つち)を潤すだろう
忘却は神の恩恵とだれかが囁く
子供らの未来のために
やすらぎの時
悠(はるか)ならんことを
地獄を美しく描いた画家
日本画家の平山郁夫氏は、昭和二十年八月六日、勤労動員先の広島で被爆した。十五歳のときであった。長年、その体験を語ることはなく、また画にしなかった。昭和五十三年、決然として筆を執る。やがて六曲一双の《広島生変図》がうまれた。
その画は、私たち日本人の原爆のイメージに違(たが)う。氏は生々しい阿鼻叫喚の地獄絵として描かなかった。人の姿はどこにもない。夕焼けのよう、ただ真っ赤に燃える広島の街と空。その大火炎の中空(ちゆうくう)に不動明王憤怒(ふんぬ)の姿がほの浮かぶ。炎は、まるで人間の業を浄める火焔とも映る。不思議な静けさを湛えた宗教画のごとき一双。赤く燃えさかる炎も、祈りの声とひびく。
画家はどんな気持ちでこの画を描いたであろう。凄惨な光景の記憶が脳裏を過(よ)ぎったに違いない。湧き上がる叫びは、糾(あざな)える縄のごとき妄執となって胸底に蠢(うごめ)いたであろう。
不動明王降魔(ごうま)の剣をもって祓わんとしたものは何であったか。赤い炎に焼き尽くさんとしたものは何であったか。画家は数十年の葛藤を経て、ついに悲劇の体験を乗り越えた。美の力をもって、情念を祈りに昇華せしめた。一筆一筆に込められたものは、魂魄の迷いではなく霊性の光であった。
氏は語っている。悲惨さや戦争の愚かさを描くのではなく、生きよというメッセージを伝えたかったと。そして美術は、たとえ惨禍を描いたとしても美しくあらねばならないと。
美は魂の栄養だ。生命を紡ぐ力でなければならない。「芸術とは自然に向かって鏡をかかげることだ」といった人がいる。自然は美そのものである。ならば、芸術は美しくあらねばならなぬ。
美しくあらんと願う心は祈りの心に他ならない。
(2007/10/19)