じゅげむ?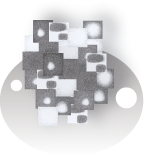
2009年 4期
己に求む
「君子は諸(これ)を己に求め、小人は諸を人に求む」。先日、産経新聞の「古典個展」欄の文末に引用されていた論語の言葉です。「諸」とは責任。君子はすべてのことを己自身の責任として捉える、小人は何でもかんでも人の責任にするという謂。
責任を己に求める者は人を安易に批判しません。逆に責任を人に求める者は批判ばかりします。
批判するとは一体どういうことなのか、これはよくよく考えるべきことです。自分自身にやるべき大事なことがあって、そのことに集中し精一杯の日々を送る人間にとっては、批判などしている暇などありません。ですから、人の事が気になって批判ばかりしている人は、きっと暇人なのだろうと想像します。
人の事などどうでもいいというのではありません。そうではなく、人のあら探しをして批判ばかりするということは、己の精神が道を求めて苦闘する、その切羽つまった希求の切実さに欠けている場合が多いということです。また自らの責任において一事をなさんとすれば、おのず事を成すことの大変さを覚らされる故に、人のことをそう簡単には批判できなくなるのです。
よって君子は黙して語らず、小人は事を論(あげつら)うてばかりいるのであります。
責任を己に求める者は人を安易に批判しません。逆に責任を人に求める者は批判ばかりします。
批判するとは一体どういうことなのか、これはよくよく考えるべきことです。自分自身にやるべき大事なことがあって、そのことに集中し精一杯の日々を送る人間にとっては、批判などしている暇などありません。ですから、人の事が気になって批判ばかりしている人は、きっと暇人なのだろうと想像します。
人の事などどうでもいいというのではありません。そうではなく、人のあら探しをして批判ばかりするということは、己の精神が道を求めて苦闘する、その切羽つまった希求の切実さに欠けている場合が多いということです。また自らの責任において一事をなさんとすれば、おのず事を成すことの大変さを覚らされる故に、人のことをそう簡単には批判できなくなるのです。
よって君子は黙して語らず、小人は事を論(あげつら)うてばかりいるのであります。
(2009/12/01)
無限から湧くもの
後藤静香(ごとう・せいこう)の詩を更に一篇。詩集『権威』の題名となった詩。
権威
詩も歌も
無限を背景としないものには
深さが無い。
真の言葉は無限から出る。
無限から湧かないならば
黙ってゐるがよい。
人を活かし、人の真心を
動かす様な権威ある言葉は
無限に触れなければ断じて出ない。
「無限から湧かないならば/黙ってゐるがよい。」
これは至言だと思います。
演奏家に置き換えれば、
「無限から湧かないならば/演奏しない方がよい」
ということです。
(2009/11/14)
権威
詩も歌も
無限を背景としないものには
深さが無い。
真の言葉は無限から出る。
無限から湧かないならば
黙ってゐるがよい。
人を活かし、人の真心を
動かす様な権威ある言葉は
無限に触れなければ断じて出ない。
「無限から湧かないならば/黙ってゐるがよい。」
これは至言だと思います。
演奏家に置き換えれば、
「無限から湧かないならば/演奏しない方がよい」
ということです。
(2009/11/14)

詩集『権威』より
前回につづき後藤静香(ごとう・せいこう)の詩を一篇。
目標
目標は何か?
念願は何か?
権勢?
黄金?
逸楽?
望んだものは与えられよう。
併し、それと同時に
望まなかったものをも
受けねばなるまい。
人生はすべてプラス・マイナスのセットで与えられように思います。
「そんなはずではなかったと」いうマイナスの部分も、
誰のせいでもない、自らが望み、自らが招いたことに違いありません。
どんな理不尽な事すらも、すべて自らの責任として捉えることができたとき、
魂は大きく成長することができるのだと思います。
人生は理屈ではありません。道理です。
批判ばかりしていると道理からはずれます。
魂は成長できません。
魂を磨くために生まれてきたのですから、
もったいないことです。
(2009/11/13)
目標
目標は何か?
念願は何か?
権勢?
黄金?
逸楽?
望んだものは与えられよう。
併し、それと同時に
望まなかったものをも
受けねばなるまい。
人生はすべてプラス・マイナスのセットで与えられように思います。
「そんなはずではなかったと」いうマイナスの部分も、
誰のせいでもない、自らが望み、自らが招いたことに違いありません。
どんな理不尽な事すらも、すべて自らの責任として捉えることができたとき、
魂は大きく成長することができるのだと思います。
人生は理屈ではありません。道理です。
批判ばかりしていると道理からはずれます。
魂は成長できません。
魂を磨くために生まれてきたのですから、
もったいないことです。
(2009/11/13)
悦べよ
焰の見えないのは燃えていないからである。
泉の溢れないのは湧いていないからである。
燃えない篝(かがり)を誰が囲むか。
湧かない泉を誰がくむか。
悦べよ!
自ら悦んでいないものは
誰をも悦ばすことが出来ないから。
これは大正から昭和にかけて活躍した社会運動家、後藤静香(ごとう・せいこう)の「悦べよ」という詩です。
『権威』(大正10年)という詩集に収められています。
当時100万部を越すベストセラーとなった詩集だそうで、私は知人から四年近く前に教えてもらいました。
古本屋ですぐに手に入れ、私にとって大事な大事な本のひとつとなりました。
「権威」とはこの世の俗世間的な権威ではなく、神のゆるぎない権威の謂です。
詩集のことばは、まさに神が乗り移ったかのごとく、峻烈な風韻の漂うて、
おのず精神の覚醒される、そんな不思議な力に満ちあふれています。
何者か高貴なる神霊に導かれなければ、このような言葉は生まれ得ない、
そう深く納得し確信させられるひびきがあるのです。
そのなかで「これぞ我が意中の言」と感得したのが「悦べよ」という詩です。
これは私自身の演奏家としての心構えそのものであります。
そう、私が目指す「光の語り」。
それは自分自身の魂が心の底から悦び、生命が躍動する、
そんな琵琶語りでありたいという願いが込められているのです。
2001年、私はそのことを自らに宣言し、そして実行に移し始めました。
本当の悦びをもって語ることのできる琵琶語りがない以上、自分自身で作しかない、
そう想ったのです。
その想いは、この詩との出会いによって確信へと変わりました。
私は徒ひたすら、己の内奥の素直な叫びに耳を傾け、毎年作品を作り続けました。
そして今年で9年目。
今年のリサイタルで発表した《役行者琵琶伝》、
この作品によってようやく、私が求めていた姿にかなり近づけたような、
そんな手応えを感じ始めています。
私の魂はいま、本当の悦びに震え始めたのです。
もう元になんか戻れません!
(2009/11/02)
泉の溢れないのは湧いていないからである。
燃えない篝(かがり)を誰が囲むか。
湧かない泉を誰がくむか。
悦べよ!
自ら悦んでいないものは
誰をも悦ばすことが出来ないから。
これは大正から昭和にかけて活躍した社会運動家、後藤静香(ごとう・せいこう)の「悦べよ」という詩です。
『権威』(大正10年)という詩集に収められています。
当時100万部を越すベストセラーとなった詩集だそうで、私は知人から四年近く前に教えてもらいました。
古本屋ですぐに手に入れ、私にとって大事な大事な本のひとつとなりました。
「権威」とはこの世の俗世間的な権威ではなく、神のゆるぎない権威の謂です。
詩集のことばは、まさに神が乗り移ったかのごとく、峻烈な風韻の漂うて、
おのず精神の覚醒される、そんな不思議な力に満ちあふれています。
何者か高貴なる神霊に導かれなければ、このような言葉は生まれ得ない、
そう深く納得し確信させられるひびきがあるのです。
そのなかで「これぞ我が意中の言」と感得したのが「悦べよ」という詩です。
これは私自身の演奏家としての心構えそのものであります。
そう、私が目指す「光の語り」。
それは自分自身の魂が心の底から悦び、生命が躍動する、
そんな琵琶語りでありたいという願いが込められているのです。
2001年、私はそのことを自らに宣言し、そして実行に移し始めました。
本当の悦びをもって語ることのできる琵琶語りがない以上、自分自身で作しかない、
そう想ったのです。
その想いは、この詩との出会いによって確信へと変わりました。
私は徒ひたすら、己の内奥の素直な叫びに耳を傾け、毎年作品を作り続けました。
そして今年で9年目。
今年のリサイタルで発表した《役行者琵琶伝》、
この作品によってようやく、私が求めていた姿にかなり近づけたような、
そんな手応えを感じ始めています。
私の魂はいま、本当の悦びに震え始めたのです。
もう元になんか戻れません!
(2009/11/02)
新・山種美術館のこと
新・山種美術館が10月1日に東京・広尾の地に開館しました。
この美術館は私にとっては思い出の深い美術館です。
美術史を専攻していた早稲田文学部時代、
何度足を運んだか数えきれません。
その当時は茅場町の山種証券ビルの8階と9階にありました。
早稲田の文学部からは地下鉄東西線一本ですぐの所にあったので、
授業の合間を縫ってはよくたづね、
独り沈々として画に向き合う、
至福の時間を過ごしました。
横山大観、上村松園、速水御舟、竹内栖鳳、小林古径など、
近代日本画のコレクションでは随一です。
常設展は入場料も安かったし、いつも人がまばらで、
ゆったりとした落ち着いた空間を味わえ、
本当にお世話になりました。
それがいつであったか移転されることになって、
しばらく千鳥ヶ淵の近くに仮設の狭い美術館がありましたが、
新美術館の開設までいったい何年待ったでしょうか・・・。
その待望の新・美術館開設。
開館記念の「速水御舟展」を心躍らせながら観に行ってきたのですが・・・、
何か満たされぬ、
何か違うなー、
という淋しい想いで帰宅したのでありました。
大好きな御舟の画のことはさておき・・・、
新・美術館は立派な建物、地下1階、地上6階。
さぞ、ゆったりと鑑賞できるのだろうと期待に胸をふくらませていたのですが、
何とびっくり、展示スペースは地下の1階だけ。
常設展はなし。
展示室に降るのも、長い長い階段でしか降りられない。
ちょっと不親切なアプローチ。
加えて、展示スペースが地下一階だけと限られているのに、
グッズ売り場がちょうど展示室の扉を入ったすぐの場所に広い空間を占拠、
これが第2展示室よりも広いときている!
これは本末転倒。
展示室への扉が開かれたとたんミュージアムショップでは、
「さあこれから画に向き合う」という期待も裏切られ、
何とも無粋ではありませんか。
あの長い長い階段は、
これから芸術の至福へ誘うための、
仕掛けではなかったのか。
まるで、
防音扉を開けて演奏会場に入ったらCD売り場が目の前にあったというような変な気分でした。
これは直ちに一階のロビーに移設すべし!
更に、第2展示室の入り口の壁が、
真っ赤なイルミネーションで照らされているのでありました。
ご丁寧なことに、その前に休憩用の椅子が置いてありますが、
バーのカウンターではあるまいし、
真っ赤な光で情念を刺激して何するぞ!
気高き御舟の画の展覧であるぞ!
すぐに普通の電球色に変えるべし!
美術館の主役は作品ではないか。
過剰な演出は無用!
作品に、自然に素直に向き合うことのできる環境を、
さりげなく調えることこそ、
美術館設計、展示設計の要諦ではないか!
第2展示室の清楚な花の小品たちは、
心なしか居心地の悪い様子でありました。
というか、私自身の心が落ち着かなかったのでありましょう。
帰り際、足の悪いおばあちゃんが、
やっとの思いで長い階段を昇ってゆく姿をみるにつけ、
いまどきの美術館の設計を何と心得ているのか!
と腹立たしい気持ちさへ湧き上がってくるのでありました。
というわけで、
ブログを書きながら、
やりきれぬ思いがさらに増して心穏やかならず。
これくらいにしておきます。
山種美術館には思い入れもあり、
ながらくリニューアルを心待ちにしていただけに、
小言ばかりになりましたが、
ご勘弁願います。
ああ〜〜、芸術は何かと面倒じゃ!
最後に御舟さんの画で、お口直しを。
この美術館は私にとっては思い出の深い美術館です。
美術史を専攻していた早稲田文学部時代、
何度足を運んだか数えきれません。
その当時は茅場町の山種証券ビルの8階と9階にありました。
早稲田の文学部からは地下鉄東西線一本ですぐの所にあったので、
授業の合間を縫ってはよくたづね、
独り沈々として画に向き合う、
至福の時間を過ごしました。
横山大観、上村松園、速水御舟、竹内栖鳳、小林古径など、
近代日本画のコレクションでは随一です。
常設展は入場料も安かったし、いつも人がまばらで、
ゆったりとした落ち着いた空間を味わえ、
本当にお世話になりました。
それがいつであったか移転されることになって、
しばらく千鳥ヶ淵の近くに仮設の狭い美術館がありましたが、
新美術館の開設までいったい何年待ったでしょうか・・・。
その待望の新・美術館開設。
開館記念の「速水御舟展」を心躍らせながら観に行ってきたのですが・・・、
何か満たされぬ、
何か違うなー、
という淋しい想いで帰宅したのでありました。
大好きな御舟の画のことはさておき・・・、
新・美術館は立派な建物、地下1階、地上6階。
さぞ、ゆったりと鑑賞できるのだろうと期待に胸をふくらませていたのですが、
何とびっくり、展示スペースは地下の1階だけ。
常設展はなし。
展示室に降るのも、長い長い階段でしか降りられない。
ちょっと不親切なアプローチ。
加えて、展示スペースが地下一階だけと限られているのに、
グッズ売り場がちょうど展示室の扉を入ったすぐの場所に広い空間を占拠、
これが第2展示室よりも広いときている!
これは本末転倒。
展示室への扉が開かれたとたんミュージアムショップでは、
「さあこれから画に向き合う」という期待も裏切られ、
何とも無粋ではありませんか。
あの長い長い階段は、
これから芸術の至福へ誘うための、
仕掛けではなかったのか。
まるで、
防音扉を開けて演奏会場に入ったらCD売り場が目の前にあったというような変な気分でした。
これは直ちに一階のロビーに移設すべし!
更に、第2展示室の入り口の壁が、
真っ赤なイルミネーションで照らされているのでありました。
ご丁寧なことに、その前に休憩用の椅子が置いてありますが、
バーのカウンターではあるまいし、
真っ赤な光で情念を刺激して何するぞ!
気高き御舟の画の展覧であるぞ!
すぐに普通の電球色に変えるべし!
美術館の主役は作品ではないか。
過剰な演出は無用!
作品に、自然に素直に向き合うことのできる環境を、
さりげなく調えることこそ、
美術館設計、展示設計の要諦ではないか!
第2展示室の清楚な花の小品たちは、
心なしか居心地の悪い様子でありました。
というか、私自身の心が落ち着かなかったのでありましょう。
帰り際、足の悪いおばあちゃんが、
やっとの思いで長い階段を昇ってゆく姿をみるにつけ、
いまどきの美術館の設計を何と心得ているのか!
と腹立たしい気持ちさへ湧き上がってくるのでありました。
というわけで、
ブログを書きながら、
やりきれぬ思いがさらに増して心穏やかならず。
これくらいにしておきます。
山種美術館には思い入れもあり、
ながらくリニューアルを心待ちにしていただけに、
小言ばかりになりましたが、
ご勘弁願います。
ああ〜〜、芸術は何かと面倒じゃ!
最後に御舟さんの画で、お口直しを。
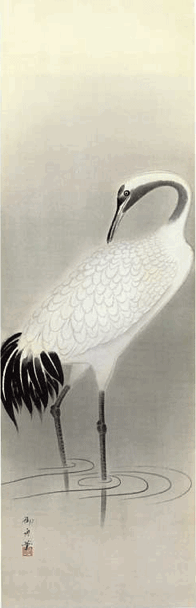
「鶴」速水御舟 昭和7年
ああ〜〜、やっぱり芸術はいい!
(2009/10/06)