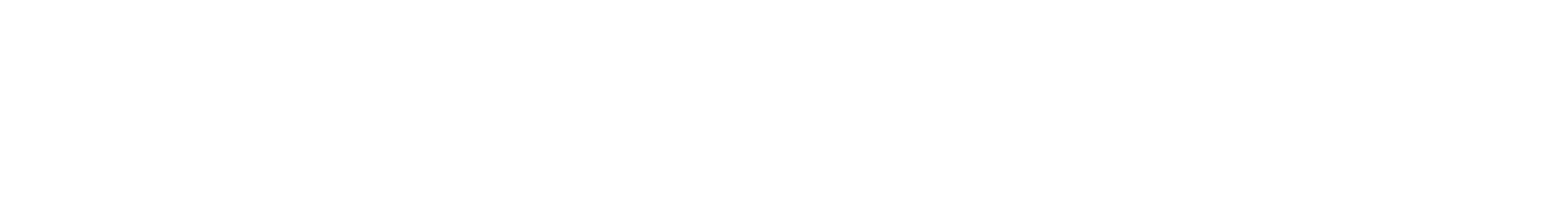21 5 月 2000
首狩り族の末裔、ということ
2000/05/24 /水曜日
今年は「関ヶ原の戦い」からちょうど400年になるそうですが、そうすると少なくともその頃までは、戦に行って敵の首を取ってくる、というのが当たり前だったわけです。「首を取る」というのは、なにかのたとえではなく、実際に戦場で相手を殺傷し、首を切り落として持ってくる。ということです。それが手柄になっていたわけです。首が無理ならば、目玉や耳や鼻を切り取って持って来ても、ある程度の手柄になったそうです。
以前、開国して間もない頃の日本を、欧米から来た人たちが撮影した写真を見た事があるんですが、そこには刑罰として、さらし首の写真がありました。街角のほこらのような建物の前に、罪人とされるひとの首が並んでいる写真です。おそらく明治のはじめの頃までは、こうした刑罰が、当たり前のこととして、おこなわれていたのでしょう。だいたい100年くらい前のことです。
「首狩り族」という言い方には、多分に蔑視する意味合いが含まれています。ある文化から見て、他の文化が野蛮に見える。でもその野蛮に見える文化にも、ある一定のルールがあり、その集団のなかには暗黙の了解があるので、無闇矢鱈に殺戮がおこなわれているわけではないのです。
ただやはり、明治以降、海外に出た一部の日本人が、外からの目でそうした風習を眺めたとき、ちょっとこれはマズイと思ったことでしょう。なんとかこの国の人間を、欧米の人たちのようにしたい。そこで考え出したのが、欧米のような唯一絶対の神を中心とした国家像だったわけです。それまで関係なかった、伝統的な神道と皇室を無理矢理いっしょにして、天皇を中心とした一神教の宗教をつくり出し、さらにそれと国家とを一体化する。その象徴として国歌としての「君が代」があるわけですね。こうして強力な宗教国家が生まれたわけです。
わが国は天皇を中心として神の国である。その国民は神の子供である。だから神の子供として恥ずかしくないおこないをするように。まあ、そんな感じです。
これがかなり効果があったのは確かです。良くも悪くも。ぼくらもいまだにその影響下にあります。やれやれ。
そんなわけで(まあ、ここまではなしたことが、どこまで正確かは判りませんが)ぼくは、自分や、周りのことなどを考えるときに、しょせんは「首狩り族の末裔」なんだからね、と考えることにしてます。首狩り族にしては、よくぞここまで来たもんだよなあ、と。そのほうが、自分を神の子供だと信じるより、より現実的で、地に足が付いてると思いません?
以前、開国して間もない頃の日本を、欧米から来た人たちが撮影した写真を見た事があるんですが、そこには刑罰として、さらし首の写真がありました。街角のほこらのような建物の前に、罪人とされるひとの首が並んでいる写真です。おそらく明治のはじめの頃までは、こうした刑罰が、当たり前のこととして、おこなわれていたのでしょう。だいたい100年くらい前のことです。
「首狩り族」という言い方には、多分に蔑視する意味合いが含まれています。ある文化から見て、他の文化が野蛮に見える。でもその野蛮に見える文化にも、ある一定のルールがあり、その集団のなかには暗黙の了解があるので、無闇矢鱈に殺戮がおこなわれているわけではないのです。
ただやはり、明治以降、海外に出た一部の日本人が、外からの目でそうした風習を眺めたとき、ちょっとこれはマズイと思ったことでしょう。なんとかこの国の人間を、欧米の人たちのようにしたい。そこで考え出したのが、欧米のような唯一絶対の神を中心とした国家像だったわけです。それまで関係なかった、伝統的な神道と皇室を無理矢理いっしょにして、天皇を中心とした一神教の宗教をつくり出し、さらにそれと国家とを一体化する。その象徴として国歌としての「君が代」があるわけですね。こうして強力な宗教国家が生まれたわけです。
わが国は天皇を中心として神の国である。その国民は神の子供である。だから神の子供として恥ずかしくないおこないをするように。まあ、そんな感じです。
これがかなり効果があったのは確かです。良くも悪くも。ぼくらもいまだにその影響下にあります。やれやれ。
そんなわけで(まあ、ここまではなしたことが、どこまで正確かは判りませんが)ぼくは、自分や、周りのことなどを考えるときに、しょせんは「首狩り族の末裔」なんだからね、と考えることにしてます。首狩り族にしては、よくぞここまで来たもんだよなあ、と。そのほうが、自分を神の子供だと信じるより、より現実的で、地に足が付いてると思いません?