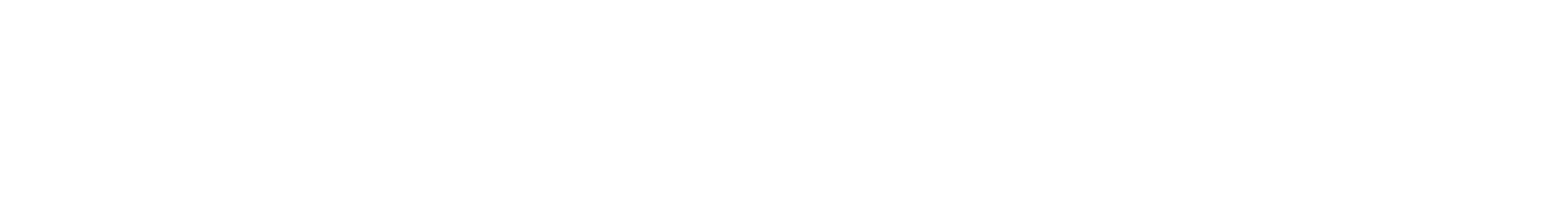映画「御法度」を見たので御法度の映画も見る(その2)
2000/04/12 /水曜日
前回からすこし間が空いてしまったので、はじめにちょっと説明しますと、いまから24年前、大島渚監督が製作し、今だ日本では完全版の公開が御法度なフランス映画「官能の帝国」(日本タイトル「愛のコリーダ」)をようやく見る事が出来た。というおはなしです。
さてぼくが見たのは、フランス語の字幕の入ったフランス製のビデオのようです。テレビ画面にあわせて多少トリミングされているかも知れませんが、おそらくこれが完全版と思っていいでしょう。
この映画については、すでにいろいろ聞いていて、先入観を持たずに見るのは難しいのですが、まあ、それが映画のテーマなので最初から最後まで性描写がつづくわけですね。でも、思ったほど露骨な描写ではありませんでした。なにか取って付けたような描写ではなく、とても自然で、あっけらかんとしていて、かつてこの国が持っていた性に対するおおらかさを感じさせます。
これはある意味、とても純粋な愛の物語です。ただ精神的なものではなく、肉体的な愛なのですが・・・。愛とは精神的なものだ、と考える人には抵抗があるのかも知れません、ぼくは素直に受け入れられましたけど。邦楽器を使った三木稔さんの音楽は、琴の奏でるメロディーが、物悲しくて美しい。三味線の音も、とてもなつかしく感じる。
ストーリーがシンプルで、いっきに昇りつめていくところが、なにか神話的な感じさえある。この映画がヨーロッパで受けるのも解るような気がします。見終わったあとに、ちょっと昇華されたような気分になる。しかしまあ、これはあくまで映画ですから、けしてマネなどしませんように・・・。
この映画がなぜ日本で御法度なのか。そりゃ子供に見せるのは考えものでしょうが、大人が見てまったく不都合はないと思います。むしろ見て損はないんじゃないですか。おそらくは、だめと言っている方でも、なぜだめなのか解らないんでしょうね。ただ、一度だめと決めたからだめなんだ、というようなことで。ちょうどなぜ日の丸が国旗で、君が代が国歌なのか、と聞いても誰も答えられないように。ただ、そうだからそうなんだ、ということで、それが勝手にひとり歩きして人間を縛る。そういう日の丸、君が代の国に、いまも生きているわけですね。
映画の終盤、定の待つ待ち合いに急ぐ吉蔵が、戦地に向かう兵隊の行進とすれ違うという有名なシーンがあります。勇ましく行進していく兵士たちを、歓喜して日の丸の小旗を振りながら見送る人々、その横を居心地悪そうに肩をすくめながらすれ違っていく吉蔵。そしてあの猟奇的な結末につづいて行くわけです。このシーンに大島監督の思いが込められているのでしょう。
もっと若い頃にこの映画を見ていたらどうだったろうと思います。いまとは性に対する感受性も、だいぶ違っていましたからね。まあしかし、なんとか今世紀中にこの映画が見られたのだから、これでよしとしましょうか。
さてぼくが見たのは、フランス語の字幕の入ったフランス製のビデオのようです。テレビ画面にあわせて多少トリミングされているかも知れませんが、おそらくこれが完全版と思っていいでしょう。
この映画については、すでにいろいろ聞いていて、先入観を持たずに見るのは難しいのですが、まあ、それが映画のテーマなので最初から最後まで性描写がつづくわけですね。でも、思ったほど露骨な描写ではありませんでした。なにか取って付けたような描写ではなく、とても自然で、あっけらかんとしていて、かつてこの国が持っていた性に対するおおらかさを感じさせます。
これはある意味、とても純粋な愛の物語です。ただ精神的なものではなく、肉体的な愛なのですが・・・。愛とは精神的なものだ、と考える人には抵抗があるのかも知れません、ぼくは素直に受け入れられましたけど。邦楽器を使った三木稔さんの音楽は、琴の奏でるメロディーが、物悲しくて美しい。三味線の音も、とてもなつかしく感じる。
ストーリーがシンプルで、いっきに昇りつめていくところが、なにか神話的な感じさえある。この映画がヨーロッパで受けるのも解るような気がします。見終わったあとに、ちょっと昇華されたような気分になる。しかしまあ、これはあくまで映画ですから、けしてマネなどしませんように・・・。
この映画がなぜ日本で御法度なのか。そりゃ子供に見せるのは考えものでしょうが、大人が見てまったく不都合はないと思います。むしろ見て損はないんじゃないですか。おそらくは、だめと言っている方でも、なぜだめなのか解らないんでしょうね。ただ、一度だめと決めたからだめなんだ、というようなことで。ちょうどなぜ日の丸が国旗で、君が代が国歌なのか、と聞いても誰も答えられないように。ただ、そうだからそうなんだ、ということで、それが勝手にひとり歩きして人間を縛る。そういう日の丸、君が代の国に、いまも生きているわけですね。
映画の終盤、定の待つ待ち合いに急ぐ吉蔵が、戦地に向かう兵隊の行進とすれ違うという有名なシーンがあります。勇ましく行進していく兵士たちを、歓喜して日の丸の小旗を振りながら見送る人々、その横を居心地悪そうに肩をすくめながらすれ違っていく吉蔵。そしてあの猟奇的な結末につづいて行くわけです。このシーンに大島監督の思いが込められているのでしょう。
もっと若い頃にこの映画を見ていたらどうだったろうと思います。いまとは性に対する感受性も、だいぶ違っていましたからね。まあしかし、なんとか今世紀中にこの映画が見られたのだから、これでよしとしましょうか。